 |
 |
| 我孫子市鳥の博物館にて |
| ●全国の湖沼水質が発表されて27年。手賀沼が初めて汚濁日本一を返上した。利根川からの導水という、土木工事的な効果が大きいとはいえ、なんとか手賀沼の環境を良くしたいという、住民の意識の現れでもある。 ●この市民ミュージカルは、「人と鳥が共存する街」にふさわしく、沼に住みついた白鳥の家族を題材に、命と自然環境の大切さを描いた。そこで、台本監修の(財)山階鳥類研究所と我孫子市鳥の博物館からも出席いただき、私たちが手賀沼の自然や鳥たちとどうつきあっていくべきかを、話し合った。 |
| ◆手賀沼の鳥や自然を大切にしたかった 下藤(原作)/私は我孫子に20年以上住んでいますが、せっかくの手賀沼がとても汚れている。昔は沼底の貝が見えるくらい、きれいな沼だったし、明治のころには、トキやコウノトリ、オオハクチョウもいたそうです。そんな手賀沼がきれいになってくれればと願い、白鳥という美しい鳥を題材に、家族の絆という視点も重ねて、この作品を書きました。 ◆鳥に親しむあまりの餌付けは、問題 杉森(山階鳥類研究所)/このミュージカルが、手賀沼にオオハクチョウやコハクチョウなどのハクチョウを呼び戻す運動に結びついていけば、すばらしいと思いますが、餌付けによる弊害も考えなくてはなりません。平成4年ころから、千葉県の本埜村の水田にハクチョウが来るようになって、いま800羽くらいに増えています。エサによってハクチョウが集まっていますが、本来は印旛沼や手賀沼のほうが、生息する環境としてはふさわしいのです。 ハクチョウが飛来した時に食べ物がないからとエサを与えることで、ハクチョウがその生活に安住してしまい、給餌場所に集中しているとの指摘も出ています。 |
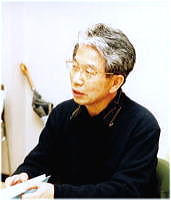 |
| 原作 下藤明男さん |
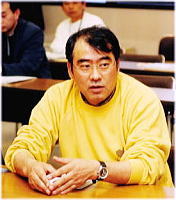 |
時田(鳥の博物館)/人間にも都合があって、吹雪の日はエサを与えに出かけるのを休むこともあります。ところが白鳥はエサをくれる人間を純真に信頼して、ずっと待っていますから、沼が凍結してしまうと、大量死につながる危険があるのです。 小菅(台本制作委員)/エサを与えて、一か所に集まりすぎてしまうと、伝染病が発生した時に全滅してしまう危険があると聞きましたが。 時田/東北地方の渡来地の多くは、家畜の飼料をあたえているようで、土壌細菌に汚染される心配も出てきています。また、本来もう少し南で越冬する白鳥が、中継地として立ち寄ったところでエサを与えられ、そこで止まってしまうのは問題であると、給餌に反対する人たちが指摘しています。 下藤/たとえば漁船が網から落としたサカナを追いかけてオジロワシが飛んできたり、田んぼがあるからドジョウがいて、それでトキがエサをとりやすい環境が生まれているとか、自然に鳥と人間が共存しているのは、よいのではないでしょうか。 ◆北へ帰らせるのが、自然の姿か 小菅/脚本化にするに当たって、自然の生態系との折り合いが難しかったですね。渡り鳥の白鳥なら、春になったら北へ帰るのが、むしろ自然ではないかという葛藤も出てきました。 下藤/その点については、自分も悩みましたが、あまり生物学的にこだわらず、自然の大切さを訴える童話として、本来のテーマの部分で感じていただければと思っています。 塚田/演出サイドとしては、主役の白鳥夫婦を、北へ帰すべきか残すべきか、「それが問題だ」というハムレットの心境ですが、ドラマを見る人の自由な気持ちで想像していただくつもりです。 ◆巣立ちビナを保護しちゃいけない? 森(実行委員長)/台本に「巣から落ちたヒナを拾っちゃいけないよ」というセリフがあるんですが、明らかにまだ飛べなくて、ネコに食べられちゃうヒナを、ほっとくべきなんでしょうか。 |
| 我孫子市鳥の博物館 主査長 時田賢一さん |
|
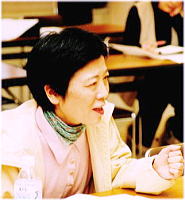 |
|
| 台本制作委員 小菅秀子さん |
| 時田/巣立ちビナは枝渡りしている時に、よく落ちてしまいます。それを巣に戻したり、高いところへ止まらせてあげるのは、構わないと思います。ただ、親鳥は近くにいますから、持って帰ってきてしまうと、「鳥さらい」になっちゃうよ、と教えています。 ◆白鳥は家族思い 丹保(作曲)/曲づくりにあたって、白鳥の気持ちを表現するのに知りたかったのが、鳥がどういう衝動で渡っていくのか、ということです。 杉森/ハクチョウやガンそしてツルは、渡り鳥の中でも家族を大切にする鳥で、家族で行動します。ツルは日本や中継地では家族で行動しますが、繁殖地に近づくと親子でも別行動をすることが、衛星を使った調査で判明しています。また、国内で繁殖する小鳥の仲間は、秋になると南に渡っていきますが、親子は別れて飛び立っていきます。親から教わることなしに、陽が短くなり、気温が下がる秋になると南の国に旅立ちます。いずれにしても、良い子孫を残すために良い環境のところへ飛び立つわけです。 丹保/私自身も、子どもをいい環境のところで育てたいと思って家を探しまして、古利根沼の森が目の前という住宅を見つけ、ああここしかないと思って、我孫子に移ってきました。良い環境で子育てをしたいという気持ちは、自然に音楽に現れてきますね。 下藤/ふるさとから離れて我孫子に住んだ人が、初めのうちは実家へ帰省していても、やがて家族ができ、だんだん我孫子が新しいふるさとになってきて、帰らなくなってくる。そんな話も良いのではないかと思いました。 ◆水鳥たちに「食べられる」手賀沼に 杉森/今の手賀沼は、多くの水鳥たちの休み場にすぎなく、エサはよそへ行って食べています。昔は手賀沼に住むさまざまな動植物をエサとして活用していましたが、今は汚染に強いモツゴ、テナガエビや、富栄養化して増えた動物性プランクトンを食べる水鳥しか、生活できない環境になっています。手賀沼が水鳥たちから「食べられる」環境になるということは、昔のように泳げる沼になることであり、沼の水を飲めるようになることです。昔は手賀沼に出かける時、お弁当は持っていっても、水筒はいらなかったといわれているくらいです。 |
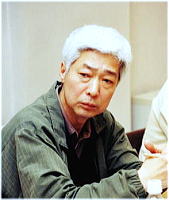 |
| 演出補 塚田一彦さん |
|
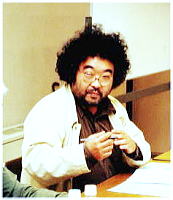 |
|
| 作曲・音楽監督 丹保剛さん |
 |
森/鳥たちに直接にエサを与えるのでなく、自然にエサが増えるような環境を、人間が作っていくことが大切。それが結局は私たち人間が生活する、良い環境につながっていくわけですね。 塚田/北千葉導水でワーストワンを抜けたというけれど、利根川の水で薄めただけじゃないか、と釣り好きな友人が言っていました。本来の水質そのものを良くする努力を、一人ひとりがどれだけしているのかを忘れないことが大切ですね。 杉森/環境を守るという視点では、釣り人が残す糸や針の弊害があげられますが、猟銃で撒き散らされるナマリ玉も問題なのです。鳥や動物がエサといっしょに食べてしまい、鉛中毒になって死ぬものがある。このミュージカルに、鳥たちが安心して暮らせる環境づくりを、われわれ人間たちがしなければといったメッセージも、合せて表現していただければ嬉しいです。 |
| ■手賀沼でくちばしに釣り糸が絡んだ白鳥 我孫子市鳥の博物館提供/2002.12.17撮影 |
| ◆グローバルな考え方への広がり 高橋信一(文化課長)/我孫子市のミュージカルとして、沼と鳥はとてもいい組合せでした。でもその中で、どうして白鳥なのかなとも思いました。 杉森/ハクチョウを題材にしたことが、とても良いと思います。渡り鳥には繁殖地があり中継地があり、越冬地があります。ハクチョウを守っていこうというのは、手賀沼の環境を良くしようというだけでなく、繁殖地や中継地も含めた、グローバルな視点で環境問題をとらえていこうという、広がりが出てくるのです。 |
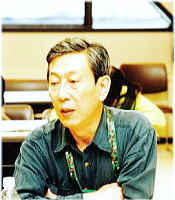 |
| 財)山階鳥類研究所 広報室長 杉森文夫さん |